ヨガ(ヨーガ)の基本、方法などを内藤景代の本で学びませんか? ヨガ・瞑想・教室(東京・新宿) NAYヨガスクール
|
nature photo 撮りたてヨガ・癒しの写真! 2010/10/31(日)
|
| ←nature photo&フォトエッセイ(内藤景代)トップへ ←ヨガの基本・方法・効果(内藤景代) TOPへ |
| ● |
●韓国版の翻訳 「3分ヨガ」が発売されました。(日本版「毎日をハッピーに変える 3分間ヨガオフィスでもお部屋でも 体とこころのお悩み解決」内藤景代・著)(4/1) こちらへ
●台湾版 『ベッドの上で簡単にできる「寝ヨガ」レッスン』が出来ました。題名は『快眠 瑜珈』(8/14) こちらへ
●NAYヨガスクールの関連ホームページの最新・更新情報はこちらへ
●ヨガ・瞑想・草花・動物たち・・・「内藤景代のフォト&エッセイ」11月1日最新号はこちらへ
●内藤景代の本が、実業之日本社から同時に「5点重版」!!
1〉『ヨガと冥想』12刷 2〉『新版こんにちわ私のヨガ』8刷 3〉『新版 綺麗になるヨガ』8刷 4〉『毎日をハッピーに変える3分間ヨガ』3刷 5〉『ハッピー体質をつくる3分間瞑想』3刷
●次回の内藤景代のヨガ・瞑想セミナー(集中講座・講習)・11月28日pm1:00〜5:00
| ★このサイトの見方 ●巻物形式になっていますから、タテにスクロールすることで、一目で前後の温度変化や、月齢、二十四節季の推移が分かります。●月齢の「満月」「新月」などは、気分の落ち込みや高揚、また天変地異、大きな事故などと呼応しているというデータもあります。●二十四節気は季節を先取りしています。●1年前の同じ月の「nature photo」と比較することで、「変わったこと」と「変わらないこと」の区別がハッキリしてきます。●「nature photo」過去のタイトル集 |
|---|
![]() ●今月の月の満ち欠け
●今月の月の満ち欠け
| |
●今月の二十四節気 寒露 10/8 霜降 10/23
--------------------------------------------------------------------
![]() この記録は、主に、東京都内の普通の川や池や公園で、お昼休みの30分程度に出会った、日常的なできごとが中心です。
この記録は、主に、東京都内の普通の川や池や公園で、お昼休みの30分程度に出会った、日常的なできごとが中心です。
毎回特別な場所に行ったり、そのために長時間を費やしたものではありません。
![]() 2010/10/31日(日) 月齢23 曇時々雨 気温(H)18.1度;(L)14.5度 《次の「新月●」11/6 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
2010/10/31日(日) 月齢23 曇時々雨 気温(H)18.1度;(L)14.5度 《次の「新月●」11/6 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
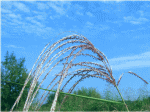 「ひとは、変われる」誰にも可能性としてある「こころの成長物語」が『BIG ME』。「自分がイヤ!」「他人とうまくいかない」、「現実はキライ!」…と感じた時が「大きな自分に出会う」旅のはじまり。「実りの秋の色」 ススキ(薄 芒)やオギ(荻)、黄色い小菊センダングサ(栴檀草) セイダカアワダチソウ(背高泡立ち草) チカラシバ(力芝)イタドリ(虎杖、痛取)の花 別名スカンポ タデ科 ノイバラ(野薔薇)の赤い実 半分だけ黄葉 カラスウリ(烏瓜)の葉 ボタンクサギ(牡丹臭木) の青い実 アケビ(通草)の薄紫の果実とツル(蔓) NAY正面 紫の葉オキザリス カタバミ(酢漿草)科 「うねるピンクの猫のシッポ」ケイトウ(鶏頭) うろこ雲(鱗雲)と絹積雲(けんせきうん) 多摩川の河原 白い雲のまん中に、満月の昼の月☆ど根性 植物☆「十薬」という別名の、ドクダミ 「ゴルゴ3毛猫 後ろへ来るな」 (詳しくはこちらへ) 写真 「イネ(稲)科の極小の花が、びっしりと咲いています。 ↑ |
●NAYヨガスクール「猫の集会」生徒さんの写真・エッセイ・演奏 2010年11月号更新しました。
![]() 2010/10/30日(土) 月齢22 大雨 気温(H)14.6度;(L)11.0度 《次の「新月●」11/6 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
2010/10/30日(土) 月齢22 大雨 気温(H)14.6度;(L)11.0度 《次の「新月●」11/6 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
日の出 6:00 日の入り 16:49 月の出 22:59 月の入り12:11 (10/30下弦)
日の出 5:54 日の入り 16:56 月の出 16:43 月の入り5:52 (10/23満月)
![]() 2010/10/29日(金) 月齢21 曇 気温(H)16.1度;(L)10.9度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
2010/10/29日(金) 月齢21 曇 気温(H)16.1度;(L)10.9度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
![]() 2010/10/28日(木) 月齢20 雨一時曇 気温(H)11.4度;(L)9.3度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
2010/10/28日(木) 月齢20 雨一時曇 気温(H)11.4度;(L)9.3度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
![]() 2010/10/27日(水) 月齢19 晴時々曇 気温(H)15.8度;(L)10.4度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
2010/10/27日(水) 月齢19 晴時々曇 気温(H)15.8度;(L)10.4度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
![]() 2010/10/26日(火) 月齢18 曇時々雨 気温(H)19.8度;(L)12.2度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
2010/10/26日(火) 月齢18 曇時々雨 気温(H)19.8度;(L)12.2度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
![]() 2010/10/25日(月) 月齢17 曇時々雨 気温(H)21.4度;(L)14.1度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
2010/10/25日(月) 月齢17 曇時々雨 気温(H)21.4度;(L)14.1度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
2010/10/24日(日) 月齢16 曇後一時雨 気温(H)18.4度;(L)13.6度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
●内藤景代の10月の「集中レッスン」(ヨガの短期集中講座・講習セミナー)<ヨガ・瞑想・呼吸法 基本と真髄>が行われました。
11月は28日(日)pm1:00〜5:00です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
2010/10/23日(土) ![]() 満月 月齢15
満月 月齢15
霜降(そうこう) 朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃
晴後薄曇 気温(H)20.2度;(L)13.2度 《次の「下弦」10/30 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 」冬の気配が現われてくる頃。 (11/7)
日の出 5:54 日の入り 16:56 月の出 16:43 月の入り5:52 (10/23満月)
日の出 5:47 日の入り 17:06 月の出 12:53 月の入り23:15 (10/15上弦)
「霜降」のこの日、最低気温13度と、急に冷え込みました。
日没も4時台になってきました。
このような季節の変化もあってか、オナガガモのオスを、川と池ではじめて見ました。
また、あのにぎやかなエナガが集団がやってきて、木から木へと、忙しく移動していました。
ハナミズキは、こんな感じに紅葉しています。(下の写真)
すでに、すべての葉を落として、赤い実だけになったものもあります。
この実をどんな鳥が食べるのだろうと思っていたら、ある日、ムクドリたちが、群がって食べているのをみました。
ムクドリのほかに、あまり鳥の姿を見かけないということは、マズイ・・・?
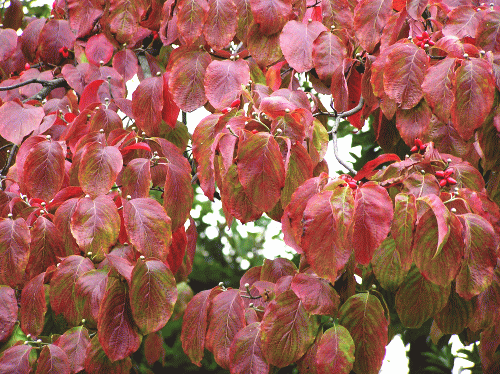
いま、ソバ(蕎麦)の花が咲いています。(下の写真)
ピンクのシベが可愛らしいです。
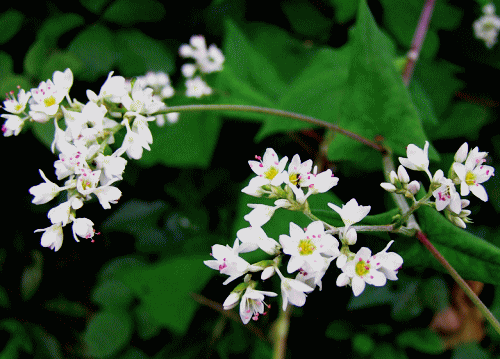
セイタカアワダチソウ(背高泡立草) キク科とアオスジアゲハです。(下の写真)
セイタカアワダチソウは、北アメリカ原産で、戦後急速に、日本全国に勢力を伸ばしました。
そのために、在来の植物を駆逐する、「ぜんそくや花粉アレルギーの原因」(全くの濡れ衣!)になるなどとも言われ、ずいぶん嫌われて、刈り取られもしました。
セイタカアワダチソウは、深さ50センチくらいのところから、養分を取るのだそうです。
その深さまで根を張る植物は、いままで日本には余りなく、その深さは、モグラやネズミがいて、豊富な肥料を蓄えていて、それを養分にして繁殖していったのだそうです。
ところがモグラも、ネズミも少なくなり、その深さでの栄養分が少なくなっても、セイタカアワダチソウは、根を短くして、浅いところから栄養をとるという仕組みにはなっていないとのこと。
そういう訳で、最近は、昔よりずっと数も少なくなり、「セイタカ(背高)」と言われた2〜3メートルの背丈も、最近はずいぶん低くなってしまっています。
なぜ、セイタカアワダチソウをあまり見かけなくなったのかの理由が分かりました。
ところが・・・
嫌われ者の、この植物は、大変有用な植物でもあるのです!
まず、蜜源植物としては、大変優秀で、急速に分布が広がったのは、養蜂業者が積極的に種子を散布したとの説もあります。
また、風評とは逆で、ぜんそくやアトピーに効く「癒しの植物」なのだそうです!
薬毒、公害、毒ガス!など毒素を排出する作用、浄血作用があり、胃腸病にも効果あり。
開花前の花穂をつんで、2,3日日向で干し、刻んでお風呂に入れて、水からわかして使用するとよいとのこと。
「悪者」という固定観念、レッテル張りは、本当によくないですね!

小さなキク(菊)が満開です。
キクとアオスジアゲハ。(下2枚の写真)
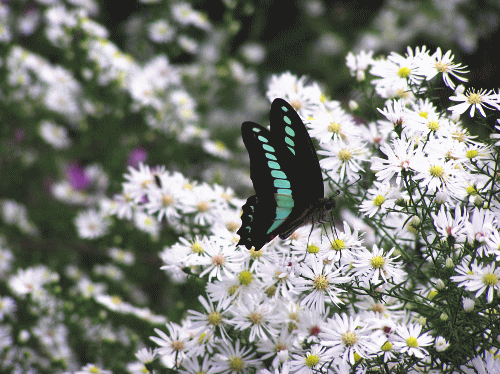
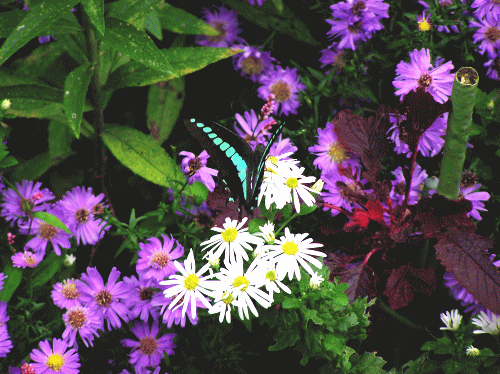
この時期に、まだナツズイセンが咲いていました!(下の写真)
写真のやや左下にツマグロヒョウモン(裏返しにとまっています。)
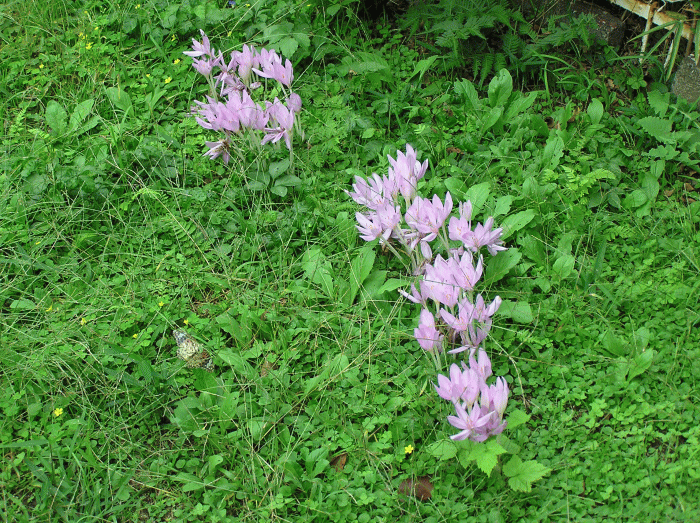
ネコたちのかくれんぼ (下3枚の写真)



参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
ハナミズキ ハナミズキ2 ハナミズキ3
ソバ![]() (←おすすめマーク)
(←おすすめマーク)
セイタカアワダチソウ![]() (←おすすめマーク)
(←おすすめマーク)
ナツズイセン
2010/10/22日(金) 月齢14 曇 気温(H)19.3度;(L)16.0度 《次の「満月●」10/23 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/21日(木) 月齢13 雨 気温(H)19.4度;(L)17.5度 《次の「満月●」10/23 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/20日(水) 月齢12 雨後曇 気温(H)20.0度;(L)17.9度 《次の「満月●」10/23 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/19日(火) 月齢11 曇 気温(H)20.6度;(L)16.7度 《次の「満月●」10/23 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/18日(月) 月齢10 薄曇時々晴 気温(H)22.7度;(L)17.1度 《次の「満月●」10/23 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/17日(日) 月齢9 曇 気温(H)24.8度;(L)18.6度 《次の「満月●」10/23 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/16日(土) 月齢8 曇後晴 気温(H)23.3度;(L)18.5度 《次の「満月●」10/23 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
(下の写真)池で。
(右端から) カモ カモ カモ カモ カモ カモ カモ カモ カメ カメ カメ カモ
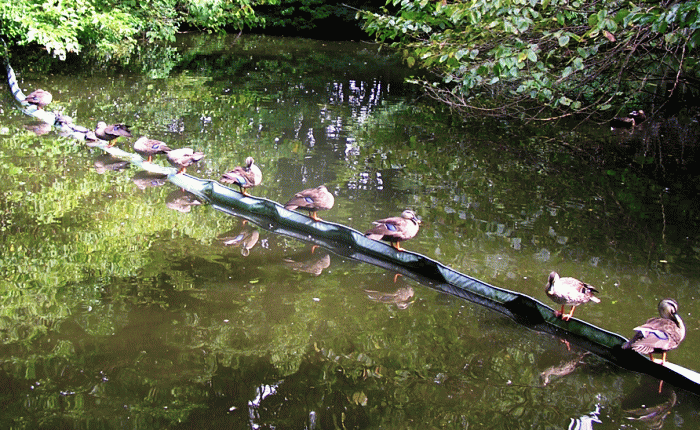
(下の写真)
左部分の拡大。
(右端から) カモ カモ カモ カモ カメ カメ カメ カモ の部分。
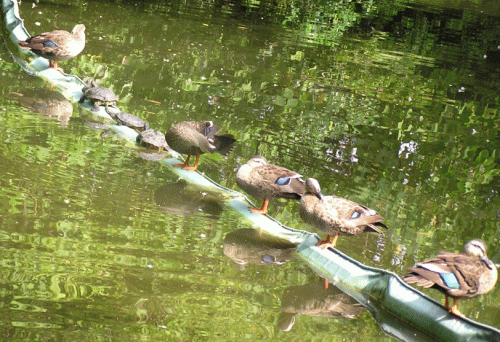
そう言えば、今年の春に生まれた9羽のカルガモのヒナたちがいましたね。
その兄弟たちかも知れません。
(下の写真)
今度は、コサギとカメ。
エサを探しながら、右の方から歩いていくと、カメが行く手を阻んでいます。
どうするでしょう?

「こりゃダメだ。」と引き返します。(下の写真)

細い脚で、綱渡りをしているようです。(下の写真)

今度は、右に移動すると、こちらにも1匹のカメが!
しかも、首を出して鋭い視線。(下の写真)

何と!またまた、すごすごと引き返します。(下の写真)

コサギがいるのを見て、ゴイサギの幼鳥が、おいしいエサでもあるのかと舞い降ります。(下の写真)
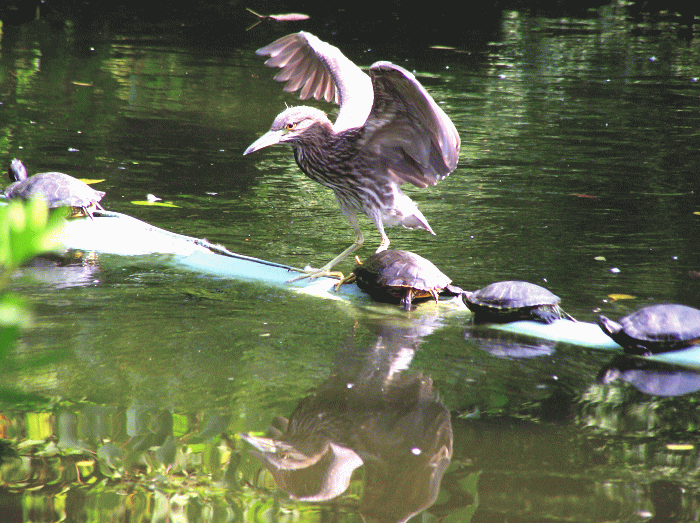
こちらも、カメとにらめっこですが、カメはゴイサギにも、四つんばいで、臆さずにらみ合い!
カメは偉大なり!?(下の写真)

こちらは、珍しいアオサギ(下の写真)

やがて、コサギは飛び去ります。(下の写真)

参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
カメ![]() (←おすすめマーク) カメ2
(←おすすめマーク) カメ2
カルガモ カルガモ2
コサギ コサギ2 コサギ3 コサギ4
2010/10/15日(金) ![]() 上弦 月齢7
上弦 月齢7
曇一時雨後晴 気温(H)23.6度;(L)19.3度 《次の「満月●」10/23 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
日の出 5:47 日の入り 17:06 月の出 12:53 月の入り23:15 (10/15上弦)
日の出 5:41 日の入り 17:16 月の出 5:59 月の入り17:08 (10/8新月)
2010/10/14日(木) 月齢6 曇後一時晴 気温(H)23.4度;(L)19.5度 《次の「上弦」10/15 次 の二十四節気は「霜降(そうこう)
」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/13日(水) 月齢5 曇後晴一時雨 気温(H)26.1度;(L)20.8度 《次の「上弦」10/15 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/12日(火) 月齢4 曇時々晴一時雨 気温(H)25.8度;(L)19.6度 《次の「上弦」10/15 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/11日(月) 月齢3 晴 気温(H)28.3度;(L)17.8度 《次の「上弦」10/15 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/10日(日) 月齢2 雨後曇一時晴 気温(H)23.6度;(L)16.8度 《次の「上弦」10/15 次 の二十四節気は「霜降(そうこう)
」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/9日(土) 月齢1 雨 気温(H)19.1度;(L)16.7度 《次の「上弦」10/15 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
*今年の北半球の夏は、130年ぶりの猛暑に見舞われましたが、冬の欧州は、一転「1000年!に一度」の厳冬に見舞われるだろ、という予想があります。アジアにもその影響が及ぶ、と。
原因は、太平洋赤道域東部の水温が平年より低くなる「ラニーニャ現象」だそうです。
また、冬も、異常気象に振り回されるのでしょうか?
*今週は、あちこちからキンモクセイ(金木犀)の香りが漂い、あのうるさいヒヨドリが、大挙して市街地に戻ってきました!

フサフジウツギとアゲハチョウ(上の写真)
後ろに、すでに枯れた花が写っています。
公園などの、生け垣風低木に咲く花などは、少し高く伸びると、安全を考えてか、すぐ花ごと刈り取られてしまいます。
昨日まで、多種なチョウやハチが群れていたアベリアの花などは、翌日には跡形もなく裸木のようにされてしまいます。
(上の写真)のフサフジウツギ(房藤空木)ですが、6月ごろから咲き始めるため、半分は枯れています。
この公園では、花が枯れた枝を切るでもなく、もちろん、木そのものを剪定もせず、自然のままに変化する姿を、いつも見ることができます。
残った花には、アゲハチョウ、セセリチョウ、ホシホウジャク、名前も知らないような蛾が次々と舞い降りて、なかなか立ち去ろうとしません。
この一角だけが、華やかで、賑やかです。

フサフジウツギとセセリチョウ(上の写真)
フサフジウツギ(房藤空木)は、中国原産で、別名ブッドレア。
蝶が大好きな花木であるところから、バタフライブッシュ Butterfly bush とも呼ばれています。
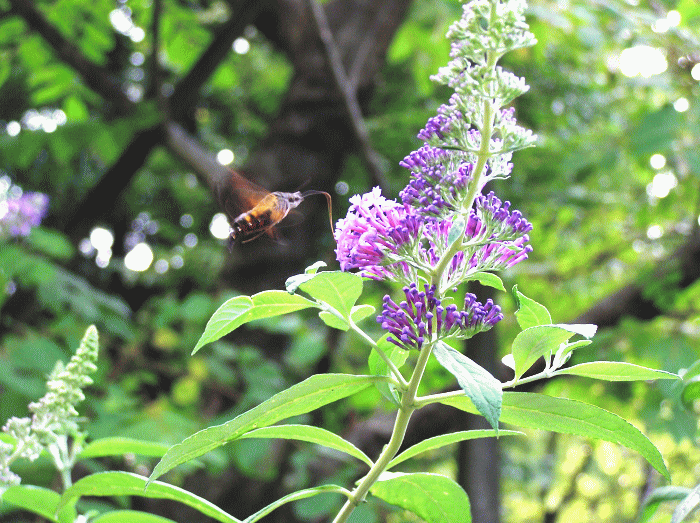

何度もご紹介している、オオスカシバが秋の深まりとともに少なくなってくると、同じスズメガ(雀蛾)科のホシホウジャク(星蜂雀)が、よく見られるようになります。
どちらも蛾なのに、ハチに似せて、昼間活動し、ホバリングしながら花の蜜を吸います。
ホシホウジャクは、オオスカシバより、数倍動きが早く、写真に撮るのに苦労します。
数十枚撮って、1枚うまく撮れているかどうか、くらいですが、(上の2枚の写真)は、吸蜜の様子がよく分かります。
正面から見ると、どことなくベビーフェイスで、お目々パッチリ、可愛いと思いませんか?(下の写真)

●過去に掲載した「nature photo・yutube動画」は、信じられないくらい、ホシホウジャクの動きをよく記録しています。撮影時期が秋の終わりのあえいか、動きがゆっくりしています。
動画でご覧下さい。 「nature photo」2008/9/19
 |
動画の終盤、ホシホウジャクの長い口の先端に花粉が付いたまま飛ぶ珍しい映像です。音声がうるさいですが、都内どこにでもある、人通りの多い普通の小径です。子どもの声がし、カラスが鳴いています。花は主にペンタス。 |
|---|
名も知れぬ、少し怪しげな蛾たち。(下の写真)


サルビア・グアラニティカにとまるキアゲハ(下の2枚の写真)
青紫の美しい花と、優雅なキアゲハ。
素晴らしい取り合わせですが、しばらく見ていると、キアゲハが居心地悪そうに、花にしがみついている様子が、伝わってくるようです。
原因は・・・・・

花の向きです!
いちばん最初に紹介した写真、フサフジウツギの花の蜜を吸うアゲハチョウは、花の向きが上を向いているから、アゲハチョウも楽ですが、サルビア・グアラニティカは下向き!
本来、アゲハチョウ向きの花ではないからです!
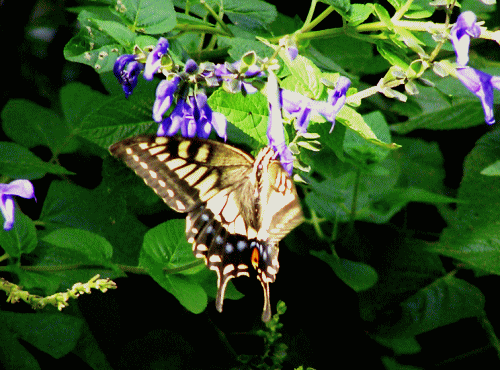
(下の写真)のホシホウジャクの場合と比較して下さい。
いかにも「ホシホウジャクさん、いらしてください。」とサルビア・グアラニティカの花が、口を開けて?呼んでいるようです!

(下の写真)は、トウワタ(唐綿)にとまるアゲハチョウです。
この写真で、キアゲハと、アゲハチョウの違いがハッキリ分かります。
アゲハは、前の羽根の上部に黒い横スジがあります。
キアゲハは、その部分に横スジはなく、薄い黒色です。

秋の花壇。(下の写真)
カクトラノオ(角虎の尾、別名・ハナトラノオ、手前)、ハゲイトウ(葉鶏頭、左中)、シオン(紫苑、奥)・・・。
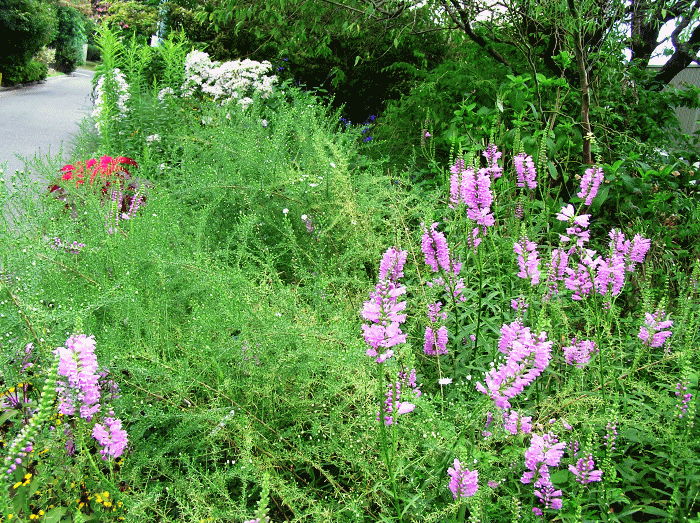
参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
フサフジウツギ(ブッドレア)
サルビア・グアラニティカとホシホウジャク サルビア・グアラニティカとホシホウジャク2
サルビア・グアラニティカとホシホウジャク3
サルビア・グアラニティカ
カクトラノオ![]() (←おすすめマーク)
(←おすすめマーク)
シオン![]() (←おすすめマーク)
(←おすすめマーク)
2010/10/8日(金) ●新月 月齢0
曇時々晴 気温(H)24.8度;(L)18.0度 《次の「上弦」10/15 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
日の出 5:41 日の入り 17:16 月の出 5:59 月の入り17:08 (10/8新月)
日の出 5:35 日の入り 17:26 月の出 22:53 月の入り12:45 (10/1下弦)
2010/10/7日(木) 月齢28 曇時々晴 気温(H)24.8度;(L)18.0度 《次の「新月●」10/8 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/6日(水) 寒露(かんろ) 露が冷気によって凍りそうになるころ
月齢27 晴 気温(H)25.7度;(L)19.7度 《次の「新月●」10/8 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 」朝夕は、霜が降りるほど冷えるようになる頃 (10/23)
2010/10/5日(火) 月齢26 曇時々晴 気温(H)26.9度;(L)19.5度 《次の「新月●」10/8 次 の二十四節気は「寒露(かんろ) 」露が冷気によって凍りそうになるころ (10/6)
2010/10/4日(月) 月齢25 曇 気温(H)22.6度;(L)18.1度 《次の「新月●」10/8 次 の二十四節気は「寒露(かんろ) 」露が冷気によって凍りそうになるころ (10/6)
2010/10/3日(日) 月齢24 曇時々晴 気温(H)24.9度;(L)17.3度 《次の「新月●」10/8 次 の二十四節気は「寒露(かんろ) 」露が冷気によって凍りそうになるころ (10/6)
2010/10/2日(土) 月齢23 晴 気温(H)24.9度;(L)19.2度 《次の「新月●」10/8 次 の二十四節気は「寒露(かんろ) 」露が冷気によって凍りそうになるころ (10/6)
萩の咲く道 (下2枚の写真)
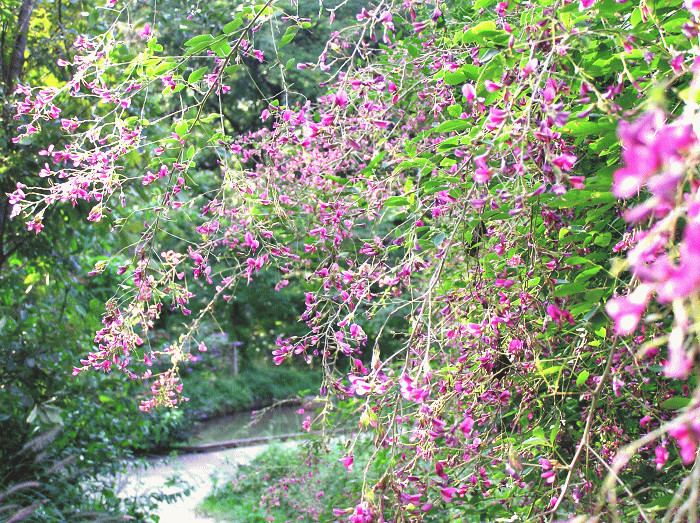
萩の向こうの、赤い花は、彼岸花。(下の写真)

チカラシバ(力芝)。夕陽が当たって神秘的。(下の写真)

ガマズミの赤い実。栄養価の高い果実酒になります。
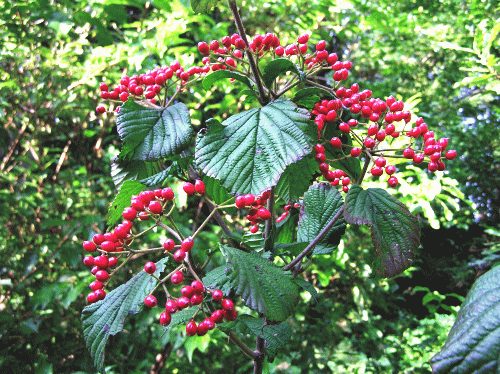
ヤブミョウガの白い花が、まだ咲いている最中に、黒い実もできて、まるで碁石を並べたようです。
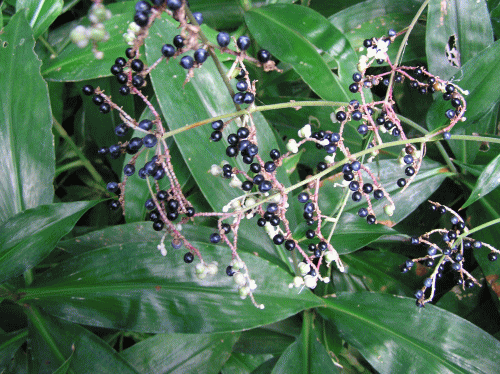
蝉の森で「怪しい人」を見た!
今年は、セミが特に多いように感じましたが・・。
一本の木に、何十匹!ものセミがとまっている木もありました。
そのような場所を、勝手に「蝉の森」と呼んでいましたが、そこである日・・・・
大きな捕虫網を手に、腰に、細長い「洗濯袋」のようなものを下げた、年配の男の人が現れました。
それから、網を使うでもなく、木にとまったセミを手づかみで、ホイ、ホイ、ホイ・・と腰の洗濯袋に、手際よく放り込んでいきました。
袋はほとんどセミでいっぱいです。
最初は、セミの研究でもしているのかとも思いましたが、どうも雰囲気が違います。
はっと思い出したのは、小さい頃見たイナゴ取りの光景です。
田んぼの稲についたイナゴ(稲子 バッタの一種)を、手づかみ次々袋に入れて、後で佃煮にして食べるのです。
立派なカルシュウム源でした。
セミをとる手つきが、いかにもそれに似ているのです。
・・・ということは、捕らえられたセミたちの運命は・・・・・?
● Wikipediaより引用
中国や東南アジア、アメリカ合衆国、沖縄などでセミを食べる習慣がある。中国河南省では羽化直前に土中から出た幼虫を捕え、素揚げにして塩を振って食べる。山東省では、河南省と同様の方法の他、煮付け、揚げ物、炒め物などで食べる。雲南省のプーラン族は夕方に弱ったセミの成虫を拾い集め、茹でて羽根を取り、蒸してからすり潰して、セミ味噌を作って食用にする。このセミ味噌には腫れを抑える薬としての作用もあるという。
沖縄でのセミ食の習慣については、同県出身のお笑い芸人の肥後克広が、子供の頃セミを焼いて食べたエピソードを紹介している。彼によれば翅と脚を除去し火で炙って食べる。特に腹腔が美味という。幼虫も食べることができる。
(下の写真)この画面だけで何匹のセミがとまっているでしょうか?

答え:手前の木に10匹、奥の木に4匹、合計14匹のようです。
こんなに見事な保護色なのですが・・・ アブラゼミ(下の写真)

紅白の「楽園」
彼岸花と2匹のアゲハチョウ。(下の写真)
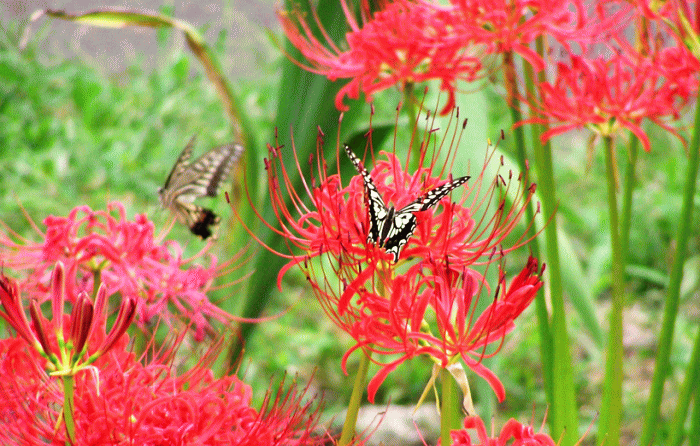
午後の日差しが、いっとき、彼岸花だけに当たって、クッキリと浮かび上がりました。(下の写真)
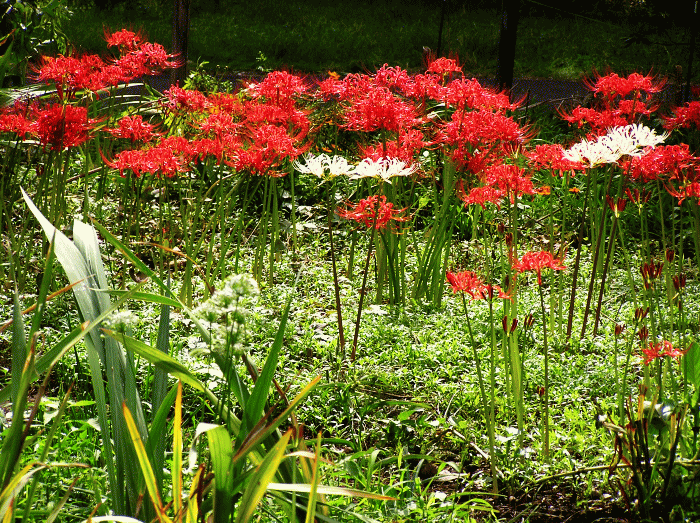
参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
ハギ ハギ2 ハギ3![]() (←おすすめマーク) ハギ4
(←おすすめマーク) ハギ4
チカラシバ
ヤブミョウガ
ヒガンバナ ヒガンバナ2 ヒガンバナ3
2010/10/1日(金) ![]() 下弦 月齢22
下弦 月齢22
曇後晴 気温(H)24.2度;(L)18.1度 《次の「新月●」10/8 次 の二十四節気は「寒露(かんろ) 」露が冷気によって凍りそうになるころ (10/6)
日の出 5:35 日の入り 17:26 月の出 22:53 月の入り12:45 (10/1下弦)
日の出 5:29 日の入り 17:37 月の出 17:13 月の入り5:08 (9/23満月)
 体の前面の「チャクラの花」といわれる部分と背面の「チャクラの根」『綺麗になるヨガ 心とからだを波動から美しく』 秋の花粉症「鼻の洗浄」「片鼻呼吸法」「冷え性直し」『毎日をハッピーに変える 3分間ヨガ』薄紫の花穂 ヤブラン(薮蘭)フイリヤブラン(斑入り薮蘭) ユリ(百合)科 サボテン(仙人掌、覇王樹)の大きな白い花 細い糸のような茶色イトトンボ(糸蜻蛉) 「見えども、見えず」 気づかないふりハチ(蜂)と人間 「知っていながら、知らない素振り」意味のある偶然=共時性(シンクロニシティ)「トトロの家」宮崎駿デザイン「(A)さんの庭(公園)」で(A)さんの庭木スダジイのお手伝い 放火の火をくい止めてくれたスダジイの「木の皮」は炭化
【生け垣囲まれた、昭和の<山の手郊外>の、ふつうの家と庭】向田邦子作品の時代の家 根岸の「子規庵」は「昭和の<下町>の、ふつうの家・仕舞た屋と庭」正岡子規
ヘチマ(糸瓜) 金目銀目の白猫(ネコ) ☆ど根性 植物☆歩道から車道にはえ広がる3つ葉のクローバー カタバミ(酢漿草) 黄色い花 寒露 霜降
(詳しくはこちらへ)
写真 「金目銀目の白猫(ネコ)」 ↑ 体の前面の「チャクラの花」といわれる部分と背面の「チャクラの根」『綺麗になるヨガ 心とからだを波動から美しく』 秋の花粉症「鼻の洗浄」「片鼻呼吸法」「冷え性直し」『毎日をハッピーに変える 3分間ヨガ』薄紫の花穂 ヤブラン(薮蘭)フイリヤブラン(斑入り薮蘭) ユリ(百合)科 サボテン(仙人掌、覇王樹)の大きな白い花 細い糸のような茶色イトトンボ(糸蜻蛉) 「見えども、見えず」 気づかないふりハチ(蜂)と人間 「知っていながら、知らない素振り」意味のある偶然=共時性(シンクロニシティ)「トトロの家」宮崎駿デザイン「(A)さんの庭(公園)」で(A)さんの庭木スダジイのお手伝い 放火の火をくい止めてくれたスダジイの「木の皮」は炭化
【生け垣囲まれた、昭和の<山の手郊外>の、ふつうの家と庭】向田邦子作品の時代の家 根岸の「子規庵」は「昭和の<下町>の、ふつうの家・仕舞た屋と庭」正岡子規
ヘチマ(糸瓜) 金目銀目の白猫(ネコ) ☆ど根性 植物☆歩道から車道にはえ広がる3つ葉のクローバー カタバミ(酢漿草) 黄色い花 寒露 霜降
(詳しくはこちらへ)
写真 「金目銀目の白猫(ネコ)」 ↑ |
●NAYヨガスクール「猫の集会」生徒さんの写真・エッセイ・演奏 2010年10月号更新しました。
内藤景代の『冥想(瞑想)―こころを旅する本』の一節に、『僕の街には、何も起こらない』という絵本の紹介があります。主人公の少年が道ばたに座り込んで、僕の街は、タイクツで、ツマラナイから、どこか遠い、別世界を夢見て、空想の世界に遊んでいる間に、彼が見ようとしない「現実」、つまり彼が住む街は、次々に事件や、出来事が起こっていく・・という絵本です。 私たちを取り巻く「世界」も、日々刻々と変化しています。 また、最近は仕事が忙しくて、空も、月も見ていない、という方々もおられます。 今、フツーの、ありふれた、まわりの自然は、どうなっているのか? その中で植物や、動物たちは、どのようにがんばって生きているのか? 都会の真ん中に住みながら、スローなまなざしと、自然をいつくしむハートでとらえた姿を、写真でありのままにお伝えできたらと願い、このページを作りました。 内藤景代の「フォト・エッセイ」の「幕間(まくあい)」としての役目も果たせたら、と思っています。 掲載された写真に関連した内藤景代の「日誌風エッセイ」の過去のページにもリンクしています。循環する「大きなとき」を感じる参考になさってください。 2005/10/15 NAYヨガスク−ル・スタッフ拝 |
|---|
*「月齢」とは 「新月の日から数えた日数のこと」 約29.53で一周する。 *温度、天候などの基準は東京です。撮影地も、主として東京都内です。 *日の出、日の入り、月の出、月の入りは、満月、新月、上弦、下弦の日に表示しています。変化を比べて下さい。 *「二十四節気」とは 簡単にいうと、太陰暦(月の運行が基準)を使っていた時代に、太陽の運行を基準にして、1年を24等分して、季節の変化を正確に知らせるために考案されたもの。1節気は、約15日 →「内藤景代のフォト・エッセイ」参照 |
|
内藤景代著「BIG ME」(NAYヨガスク−ル刊) 内藤景代著『家庭でできるビューティ「ヨガ」レッスン』(PHP研究所刊) |
| ヨガと瞑想に関するHPのご紹介 |
新しいサイトができました! 1 |
| エヌ エ−ワイ 東京・新宿・ヨガ教室 since1976 | ヨガと冥想(瞑想)NAYヨガスク−ル |
| NAY SPIRIT IS BODY TRIP& MIND TRIP to SOUL in HEART ●内藤 景代(Naito Akiyo)主宰 mail: e@nay.jp http://www.nay.jp/ |
|
| 〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-19 金光コーポ 201 |
専用FAX 03-5934-6723 24時間受付 TEL 03-3203-3831 |