ヨガ(ヨーガ)の基本、方法などを内藤景代の本で学びませんか? ヨガ・瞑想・教室(東京・新宿) NAYヨガスクール
|
nature photo 撮りたてヨガ・癒しの写真! 2009/8/31(月)
|
| ←nature photo&フォトエッセイ(内藤景代)トップへ ←ヨガの基本・方法・効果(内藤景代) TOPへ |
| ● |
![]() ●台湾版 『ベッドの上で簡単にできる「寝ヨガ」レッスン』が出来ました。題名は『快眠 瑜珈』(8/14) こちらへ
●台湾版 『ベッドの上で簡単にできる「寝ヨガ」レッスン』が出来ました。題名は『快眠 瑜珈』(8/14) こちらへ
●NAYヨガスクールの関連ホームページの最新・更新情報はこちらへ●月刊誌『毎日が発見』 2009年1月号 (角川SSコミュニケーションズ)
「朝晩5分でラクラク体調管理 ベッドやふとんですぐできる寝ヨガ」掲載中
●ヨガ・瞑想・草花・動物たち・・・「内藤景代のフォト&エッセイ」9月1日最新号はこちらへ
● 『ベッドの上で簡単にできる「寝ヨガ」レッスン〈快眠・ヨガCD付>』(実業之日本社)重版!販売中。こちらへ→●Amazon
●内藤景代の本が、実業之日本社から同時に「5点重版」!!
1〉『ヨガと冥想』12刷 2〉『新版こんにちわ私のヨガ』8刷 3〉『新版 綺麗になるヨガ』8刷 4〉『毎日をハッピーに変える3分間ヨガ』3刷 5〉『ハッピー体質をつくる3分間瞑想』3刷
●次回の内藤景代のヨガ・瞑想セミナー(集中講座・講習)・9月27日pm1:00〜5:00
| ★このサイトの見方 ●巻物形式になっていますから、タテにスクロールすることで、一目で前後の温度変化や、月齢、二十四節季の推移が分かります。●月齢の「満月」「新月」などは、気分の落ち込みや高揚、また天変地異、大きな事故などと呼応しているというデータもあります。●二十四節気は季節を先取りしています。●1年前の同じ月の「nature photo」と比較することで、「変わったこと」と「変わらないこと」の区別がハッキリしてきます。 |
|---|
2009/8/31(月) 月齢10.7 大雨 気温(H)22.2度;(L)17.6度 《次の「満月●」は9/5 次 の二十四節気は「白露(はくろ) 大気が冷えて来て、露が出来始める頃。」(9/7)
台風11号が関東に接近。
● ヨガ・瞑想・自然「内藤景代のフォト・エッセイ」2009年9月号更新しました。
 |
 |
●NAYヨガスクール「猫の集会」生徒さんの写真・エッセイ・演奏 2009年9月号更新しました。
2009/8/30(日) 月齢9.7 雨時々曇一時晴 気温(H)32.3度;(L)25.1度 《次の「満月●」は9/5 次 の二十四節気は「白露(はくろ) 大気が冷えて来て、露が出来始める頃。」(9/7)
衆議院議員選挙
民主党308議席、自由民主党119議席で、「政権交代」が実現。
2009/8/29(土) 月齢8.7 晴時々曇 気温(H)32.3度;(L)25.1度 《次の「満月●」は9/5 次 の二十四節気は「白露(はくろ) 大気が冷えて来て、露が出来始める頃。」(9/7)
2009/8/28(金) 月齢7.7 晴 気温(H)31.4度;(L)23.8度 《次の「満月●」は9/5 次 の二十四節気は「白露(はくろ) 大気が冷えて来て、露が出来始める頃。」(9/7)

(上の写真)で、池の上に、はうように伸びた木の枝の先に、「ゴミの山」のようなものが見えます。
この「ゴミの山」のようなものが、実は、カイツブリの「浮き巣」として知られている「巣」なのです。
古くから、和歌などに「にお(カイツブリの古い呼び名)の浮き巣」として、「はかないこと」「不安定なこと」の象徴として歌われたりしてきました。
水辺の葦(あし)の間などに作られた巣が、水や風の状態で揺れ動き、浮いているように見えることで、このように言われてきたものです。
しかし、実際は「浮いている」のではなく、しっかりした支えの上に、草や枝を積み上げて作っているのが本当のようです。
カイツブリは小さな水鳥とはいえ、ヒナたちとしばらく巣の上で生活するには、相当な重さがかかり、浮き続けることは不可能なようです。
それにしても、大変な技術と勤勉さであることは間違いありません。
(上の写真)の「浮き巣」は、結局大雨で壊れて、跡形もなくなってしまいました。

(上の写真)は、また新しく作った巣です。
池から突き出た木の枝を支えにしているようです。
1羽が卵を抱えています。
右にもう1羽が待機しています。
どちらがオスかメスか分かりませんが、夫婦で交代して卵を抱えます。

(上の写真)は、たまたま親が立ち上がって、3個の卵が見えました。
手前の親鳥は、木の枝をくわえ、巣を補強しているところです。
ヒマがあると、絶え間なく、葉っぱや木の枝などで補強しています。
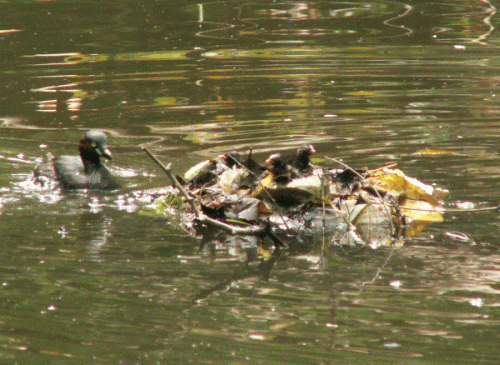
そして、ついに待望のヒナが3羽誕生しました!(上の写真)
浮き巣の上の、オレンジ色のくちばしがヒナです。
こうして見ると、カイツブリにとっては、ヒナも巣も一緒に「ゴミの山」に見えた方が、敵を欺き、好都合であることが分かります。

このような、カイツブリ親子の写真を、初めて見たひとはビックリでしょう。(上の写真)
2羽が、親の背中に乗っています!
どうなってるんだ?
「カイツブリは、ヒナを背中に乗せる」ということを読んだり、写真で見たりはしていましたが、実際に見たのは初めてでした。
背中に乗せるのは、生まれてから数日間だけだそうです。
その後は重くなってムリなのでしょう。
どのように乗せるかというと、親鳥は、一番外側にある翼を、少し持ち上げます。
そこにできた後の方の隙間に、ヒナは、頭から入っていきます。
そして、時々、親の前部の翼の合わせ目の部分から、頭を出します。
逆に、お尻の方から、頭を出す場合もあります。
キケンだと思うと、入り込んだままで、外からは、ヒナの姿は全く見えません。

(上の写真)は、巣の近くで、親からエサをもらっているところ。
トンボをもらって、食べているところも見ました。

さて、それから一週間以上たったある日。
巣にヒナの姿がまったく見えないので、心配して、池の反対側に回ってみました。
最初は、親鳥が1羽だけに見えたのですが・・・、何と背中に1羽のヒナが!(上の写真)
「カイツブリが、ヒナを背中に乗せて泳いでいるのを見たい」という願いは、一応かなえられました。
「一応」という意味は、ヒナ全員ではなく、1羽だけだったからです。
残りの2羽は、残念ながら、いなくなっていました。
カイツブリも、年々生存環境が厳しくなっているようです。
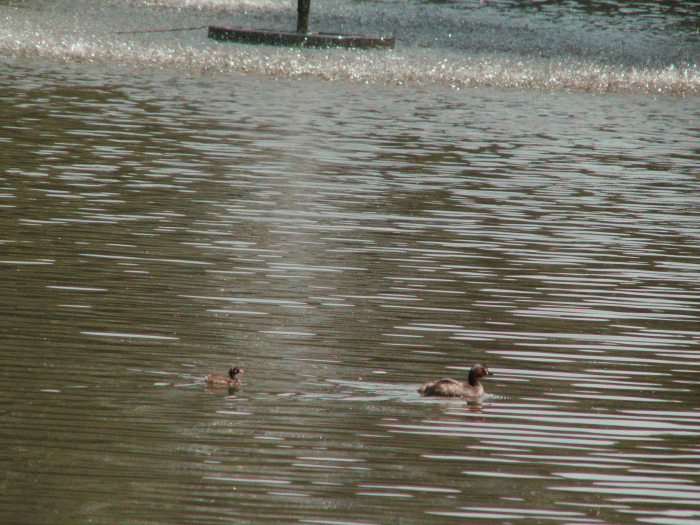
やがて、ヒナは親の背中から下りて、親の後を追い、池の噴水の近くを、ゆったりと泳いでいきます。(上の写真)
のどかで、ほのぼのとして、いつまでもこのシーンが続いてくれたらと思いました。
![]() 参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
カイツブリと浮き巣
2009/8/27(木) 上弦 月齢6.7 晴 気温(H)29.6度;(L)21.1度 《次の「満月●」は9/5 次 の二十四節気は「白露(はくろ) 大気が冷えて来て、露が出来始める頃。」(9/7)
日の出 5:09 日の入り 18:16 月の出 12:25 月の入り 22:05(8/27上弦)
日の出 5:04 日の入り 18:25 月の出 4:31 月の入り 18:07(8/23新月)
2009/8/26(水) 月齢5.7 曇後一時晴 気温(H)27.6度;(L)22.4度 《次の「上弦」は8/27 次 の二十四節気は「白露(はくろ) 大気が冷えて来て、露が出来始める頃。」(9/7)
2009/8/25(火) 月齢4.7 晴時々曇 気温(H)27.7度;(L)22.7度 《次の「上弦」は8/27 次 の二十四節気は「白露(はくろ) 大気が冷えて来て、露が出来始める頃。」(9/7)
2009/8/24(月) 月齢3.7 曇時々晴一時雨、雷を伴う 気温(H)30.2度;(L)24.2度 《次の「上弦」は8/27 次 の二十四節気は「白露(はくろ) 大気が冷えて来て、露が出来始める頃。」(9/7)
2009/8/23(日) 処暑(しょしょ) (暑さが峠を越えて後退し始めるころ。) 月齢2.7 曇時々晴後一時雨 気温(H)30.7度;(L)24.1度 《次の「上弦」は8/27 次
の二十四節気は「白露(はくろ) 大気が冷えて来て、露が出来始める頃。」(9/7)
●内藤景代の8月の「集中レッスン」(ヨガの短期集中講座・講習セミナー)<ヨガ・瞑想・呼吸法 基本と真髄>が行われました。
9月は27日(日)pm1:00〜5:00です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
2009/8/22(土) 月齢1.7 気温(H)31.6度;(L)24.7度 《次の「上弦」は8/27 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
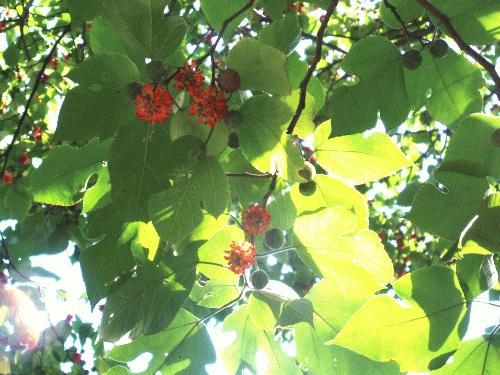
これは、なんでしょう?(上の写真)
木の実の横に、赤い花のようなものが・・。
調べてみると、これはカジノキ(梶の木)、クワ科コウゾ属の実でした。
青い実が熟すと、上の写真のように、赤い花弁のようなものが出てきます。
中を割ると、その中に、さらに小さい赤い実があって、食べると甘くておいしいのだそうです。
そのときは知りませんでしたので、食せず残念でした。
クワ科、クワの実の連想でいくと、食べれるかも?ですね。
今の人間は、このことは、あまり知りませんので、カラスの大好物になっているそうです。
ヤマボウシの赤く色づいた実を思い出しました。
カジノキの葉も独特のカタチで、昔から神様へのお供え物を、この葉の上に乗せて供した「ご神木」です。
有名な、長野県の諏訪大社の神紋となっているそうです。

(上の写真)はなんでしょうか?
ススキに覆われた日陰です。
薄紫色の花をつけで、ニョキッと地上から生えています。
一度紹介したことがありますが、
ススキなどの根元に生えている植物で、ナンバンギセル(南蛮煙管) 、ハマウツボ科です。
自分では光合成せずに、ススキや、サトウキビ、ミョウガに寄生しますので、葉っぱがありません。
名前は、西洋のキセルに似ているところからつけられましたが、万葉集に、すでに「思草(おもいぐさ)」と呼ばれて、詠まれているそうです。

このトンボは?(上の写真)
とまっている草の実と同じような色ですが・・。
ショウジョウトンボのメスです。
オスは真っ赤。
とても同じ種類とはおもえないでしょう。

(上の写真)は、アシの根元での、ギンヤンマの交尾シーンです。
このとき以外は、池の上をビュンビュン飛び回って、まったくとまってくれませんので,
写真にとれません・・。

その上の方、アシの枝に、突然カワセミが!(上の写真)
超・都心の公園なのですが・・、初めてのことで、ビックリしました。

やがて、カワセミは、池のやや奥まった木の枝に、こちらがつきあいきれないほど長く、とまっていました。
その間、多くのかたが、その前を歩いて行きましたが、だれも気づくひとはいませんでした。
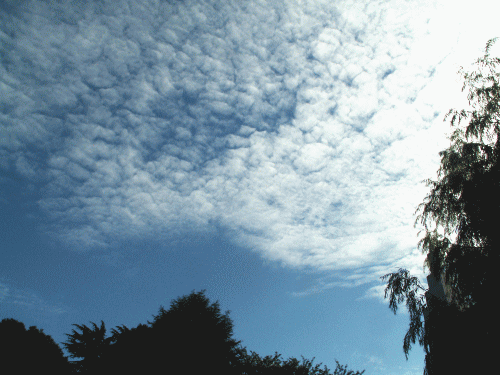
空には、入道雲に代わって、もうこんな雲がでています。(上の写真)
季節は、確実に変わりつつあるようです。
![]() 参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
ヤマボウシの赤い実
トンボ トンボ(2) トンボ(3) トンボ(4)
2009/8/21(金) 月齢0.7 曇後時々晴 気温(H)32.5度;(L)26.1度 《次の「上弦」は8/27 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
2009/8/20(木) 新月● 月齢29.0 薄曇時々晴 気温(H)31.6度;(L)25.3度 《次の「上弦」は8/27 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
日の出 5:04 日の入り 18:25 月の出 4:31 月の入り 18:07(8/23新月)
日の出 4:59 日の入り 18:32 月の出 22:48 月の入り 12:53(8/14下弦)
2009/8/19(水) 月齢28.0 薄曇一時晴 気温(H)31.3度;(L)25.0度 《次の「新月●」は8/20 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
2009/8/18(火) 月齢27.0 曇時々晴 気温(H)30.1度;(L)23.9度 《次の「新月●」は8/20 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
2009/8/17(月) 月齢26.0 晴 気温(H)30.8度;(L)23.6度 《次の「新月●」は8/20 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
2009/8/16(日) 月齢25.0 晴 気温(H)33.2度;(L)22.7度 《次の「新月●」は8/20 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
2009/8/15(土) 月齢24.0 気温(H)31.7度;(L)23.7度 《次の「新月●」は8/20 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)

(上の写真)の花はフサフジウツギ(房藤空木)です。
トラノオのような花ですが、中国原産の落葉低木で、花も大ぶりです。
(見方によっては、花で飾ったゾウ(象)さんのようにも見えます。)
5メートルほどの高さになるものもあるとか。
やがて、ヨーロッパで品種改良され「ブッドレア」という名前で、日本でも栽培されるようになりました。
派手な形と、強い芳香でたくさんの虫や蝶が集まることから「チョウの木 Butterfly Bush」と呼ばれているそうです。
この写真では、右にセセリチョウ、左にマメコガネがいます。

(上の写真)では、上部右と左に、それぞれマメコガネがいますが、中央の茶色い色の生き物は何でしょうか?
両腕をバタフライで泳ぐように両側につけた、小さなカニ?のようでもありますが・・・
これは、ガザミグモという名前のカニグモの一種です。
糸を張って、獲物を捕らえるのではなく、このように花の中にじっとして、獲物が来るのを待ちかまえ、長い脚?ではさんで捕らえます。
このカニグモ科のなかに、宇宙人のような顔をしたクモとして、時々話題になるハナグモがいます。

(上の写真)は、2回目のご紹介になりますが、本来東京にいるのがおかしい、アカボシゴマダラです。
日本では、奄美諸島にのみいるチョウで、中国、台湾、韓国などには、広く分布します。
従って、中国産が、マニアによって放たれたのでは、という説が有力です。
東京で、初めて発見されたのが3年前、温暖化などで、環境に適応しつつあるようです。
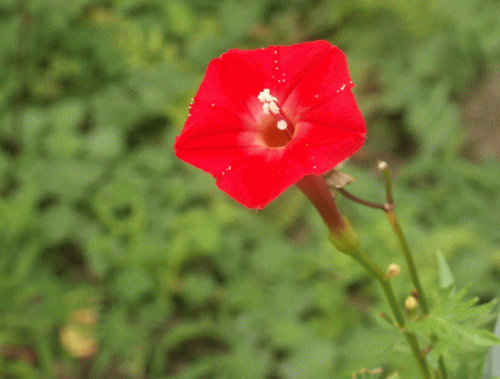
(上の写真)は、いかにも熱帯的なルコウソウ(縷紅草)です。
縷(る)とは、糸のように細長いこと。
熱帯アメリカ原産、ヒルガオ科。
星形の花のものと五角形のものがありますが、これは五角形。
葉も糸のように細いものと、もみじのような葉のものとあって、これはもみじ葉です。
●さて、11日は、台風の影響で、前日から大雨でしたが、明け方に、かなり大きな地震がありました。
その前々日にも起こっています。
関東大震災は、1923年9月1日に起こり、10万5千人の死者・行方不明者を出しました。
「備えあれば、憂いなし」
一度、身の回りを点検してみても、損はないでしょう。(8/11の項、参照のこと!)

台風の大雨が上がって、川へ行ってみると、例のカルガモ親子は<全員無事>でした。(上の写真)
増水時は、この川岸から1,2メートル上にまで、水位は上昇していたと思いますが、そのときは、どこか、もっと上の方に避難して、水が引けると、しっかりした石造りの川岸、しかも、すこし先に、上へ逃げられる階段がある場所に移動したものと思われます。
やはり、賢いです!

カワセミもやってきていました。(上の写真)
しかし、川の水は濁って、魚の影はまったく見えません。
そのせか、、あきらめて、このポーズは、ひょっとして眠っているのでしょうか?
![]() 参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
トラノオとカニグモ
カニグモ
ルコウソウ
2009/8/14(金) 下弦 月齢23.0 曇後一時晴 気温(H)30.7度;(L)25.7度 《次の「新月●」は8/20 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
日の出 4:59 日の入り 18:32 月の出 22:48 月の入り 12:53(8/14下弦)
日の出 4:53 日の入り 18:41 月の出 18:43 月の入り 4:46(8/6満月)
2009/8/13(木) 月齢22.0 曇一時雨後晴 気温(H)31.7度;(L)24.4度 《次の「下弦」は8/14 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
夜中から明け方、「ペルセウス座流星群」
2009/8/12(水) 月齢21.0 晴時々曇 気温(H)30.6度;(L)24.0度 《次の「下弦」は8/14 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
2009/8/11(火) 月齢20.0 曇時々雨一時晴 気温(H)29.1度;(L)25.0度 《次の「下弦」は8/14 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
AM 5:07 駿河湾を震源とする大きな地震。
静岡県静岡県中西部と伊豆半島で震度6弱。
東京、震度4。
台風9号の影響で、各地で大雨。
●「神戸大震災」をきっかけに設立された「NPO法人 大気イオン地震予測研究会e-PISCO(理事長 弘原海 清)」は、すでに8月7日付けのFAXで、<「首都圏大地震」が、8月末から9月末に発生公算>と警告しています。
http://www.e-pisco.jp/
何事も起こらなければ結構ですが、十分注意してください。
2009/8/10(月) 月齢19.0 大雨後曇 気温(H)28.6度;(L)25.0度 《次の「下弦」は8/14 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
2009/8/9(日) 月齢18.0 曇後一時雨、雷を伴う 気温(H)32.1度;(L)25.1度 《次の「下弦」は8/14 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
PM7:56 東海道南方沖を震源とするやや強い地震。
東京、千葉、埼玉、栃木、茨城、福島、宮城の各都県で震度4を観測。
2009/8/8(土) 月齢17.0 曇 気温(H)30.4度;(L)25.5度 《次の「下弦」は8/14 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
2009/8/7(金) 「立秋(りっしゅう) 初めて秋の気配が表われてくる頃。」 月齢16.0 曇一時晴 気温(H)33.2度;(L)25.3度 《次の「下弦」は8/14 次 の二十四節気は「処暑(しょしょ) 暑さが峠を越えて後退し始めるころ。」(8/23)
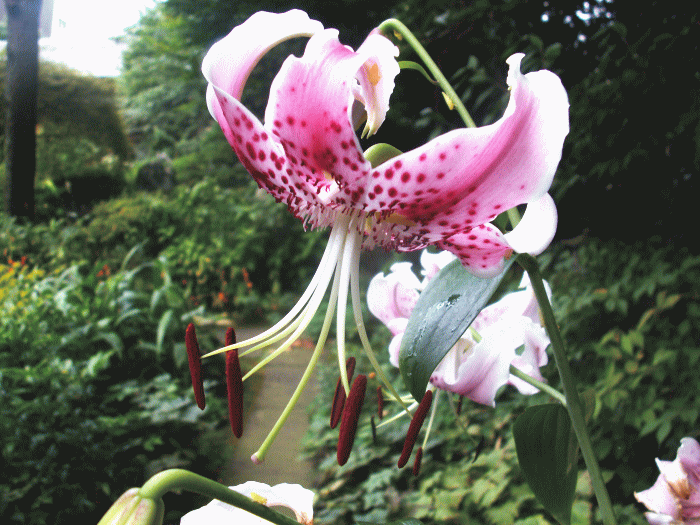
とうとう、夏らしい日々もあまりないままに「立秋」となってしまいました。
「立秋」と意識するせいか、この日から、夜など、虫の鳴き声をハッキリと聞くようになりました。
(上の写真)はカノコユリ(鹿の子百合)です。
花弁の赤い斑点が、鹿の子模様であることからカノコユリと呼ばれます。
咲く時期から、ドヨウユリ(土用百合)、タナバタユリ(七夕百合)とも呼ばれます。
主に、九州、四国に自生しますが、絶滅危惧種。
人による採集被害の他、イノシシに食べられることなども原因のようです。
(下の写真)は、シロカノコユリ。
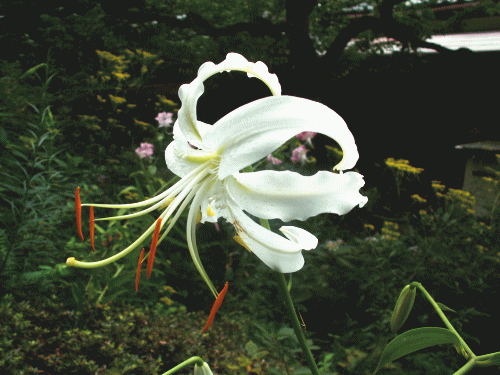
いちばん(上の写真)の左奥に写っているオレンジ色の点は、ホオズキ(鬼灯、酸漿)です。(下の写真)
オレンジ色のホオズキを死者の霊を導く提灯に見立てて、お盆に飾る習慣があります。
浅草の浅草寺の「ほおずき市」は7月9日10日。
7月10日が、昔から、「四万六千日(しまんろくせんにち)」と呼ばれる「功徳日(くどくび)とされました。
この日にお参りすると「46,000日分(約126年分)に相当する」功徳がある、という日です。
それにちなんだ縁日として、江戸時代からホオズキが売られるようになったようです。
昔は、ホオズキの、虫封じなどの薬効でも珍重されたのでしょう。

前日は、一時的に集中豪雨となりました。
川へ行ってみると、久しぶりに、2羽のカワセミ!!
少なくとも奥の1羽は、この春に巣立ったヒナのような気がします。(下の写真)
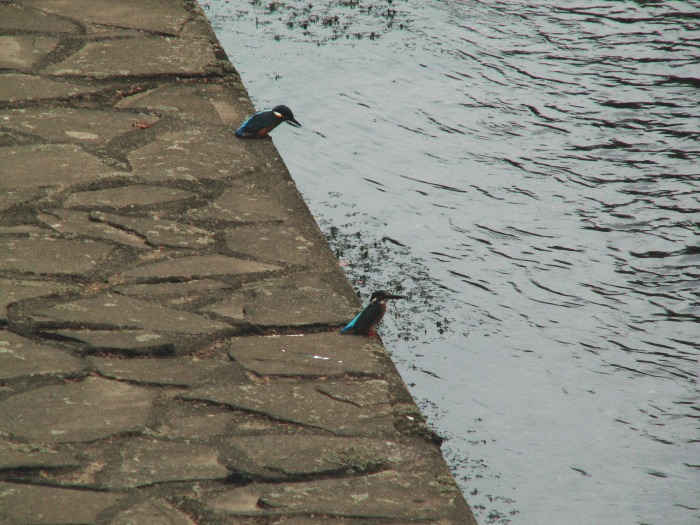
背中の翡翠(ひすい)色も、鮮やかになっていました。(下の写真)
巣立ち以来、まったく姿を見かけませんでしたが、元気に育っていて、たまには戻って来ているようで、ほっとしました。
●カワセミのヒナたちのお話は、「nature photo」2009年6月(6/6、6/20)をご覧下さい。

(下の写真)は、7月25日にご紹介したカルガモ親子です。
最初の8羽は、依然元気で、皆一緒でした。
最近、こういうケースは少ないので、うれしくなります。
一日に1羽ずついなくなる、という悲惨な例もありました。
確かに8羽います。
数えてみて下さい。

ヒナたちは、随分大きくなっていました。(下の写真)

しばらくして、対岸から、この親子を見てみました。(下の写真)
確かここにいたのですが・・・・???
河原にいるのは、成鳥のグループ。
そのいちばん上、中央に休んでいるのが親鳥です!!
ではヒナたちはどこに消えたのか??
まったく見えません!!

ところが、角度をちょっと変えて見ると・・・、
こういうことでした!(下の写真)
ジュズダマ?の葉の下に、8羽全員が見事に隠されています。
何とも、忍者のような鮮やかな術で、この母親が8羽を無事育て上げている秘密を垣間見たような気がしました。
周辺は、前日の川の水かさの増加を物語るように、ゴミなどでキタナイですが・・。

![]() 参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
ユリ ユリ(2)
ホオズキ ホオズキ(2)
カワセミ
カルガモ親子 カルガモ親子(2) カルガモ親子(3)
2009/8/6(木) 月齢15.0 曇時々雨 気温(H)30.5度;(L)25.8度 《次の「下弦」は8/14 次 の二十四節気は「立秋(りっしゅう) 初めて秋の気配が表われてくる頃。」(8/7)
日の出 4:53 日の入り 18:41 月の出 18:43 月の入り 4:46(8/6満月)
日の出 4:46 日の入り 18:48 月の出 12:33 月の入り 22:47(7/29上弦)
2009/8/5(水) 月齢14.0 曇一時晴 気温(H)30.0度;(L)24.9度 《次の「満月●」は8/6 次 の二十四節気は「立秋(りっしゅう) 初めて秋の気配が表われてくる頃。」(8/7)
2009/8/4(火) 月齢13.0 曇時々雨後一時晴 気温(H)29.6度;(L)23.2度 《次の「満月●」は8/6 次 の二十四節気は「立秋(りっしゅう) 初めて秋の気配が表われてくる頃。」(8/7)
2009/8/3(月) 月齢12.0 曇一時晴 気温(H)30.3度;(L)23.3度 《次の「満月●」は8/6 次 の二十四節気は「立秋(りっしゅう) 初めて秋の気配が表われてくる頃。」(8/7)
2009/8/2(日) 月齢11.0 雨時々曇 気温(H)26.4度;(L)22.6度 《次の「満月●」は8/6 次 の二十四節気は「立秋(りっしゅう) 初めて秋の気配が表われてくる頃。」(8/7)
2009/8/1(土) 月齢10.0 曇後一時晴 気温(H)29.0度;(L)21.6度 《次の「満月●」は8/6 次 の二十四節気は「立秋(りっしゅう) 初めて秋の気配が表われてくる頃。」(8/7)

長梅雨!の合間に、こんな入道雲が出た日もありました。(上の写真)
今年は、梅雨明けが異常に遅れていて、入道雲の出番も少ないようです。
左側の木に咲いている白い花は、エンジュの花です。
「槐」と書きますが、由来は、昔、エンジュの木でお面を作り、家の鬼門に置いたからだそうです。
難産のときには、この木の枝を握らせたとか。
安産、長寿、幸せの木とも言われ「延寿」と書く場合もあります。
中国では、高貴な木とされ、学問と権威のシンボルとされています。
いま、公園や街路樹のある道路で、白い花がいっぱい落ちて真っ白なのは、エンジュです。
意外に数が多いのに驚かされます。
エンジュの花。(下の写真)
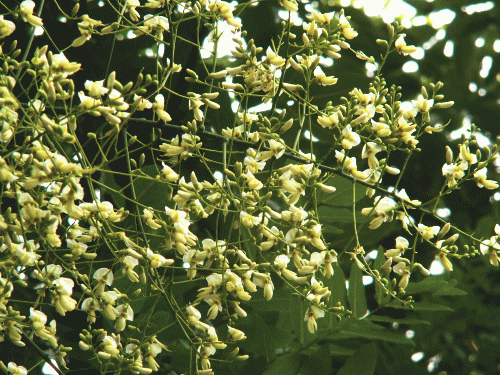
ところが、ハリエンジュ(針槐)という名前の木もあります。
エンジュは中国原産で、大昔に中国からもたらされたマメ科エンジュ属。
一方、ハリエンジュは、北米原産のマメ科ハリエンジュ属。
こちらは、5、6月に白い房状の藤のような花をつけます。
名前のように、幹にトゲ(針)がついています。
明治時代に輸入されましたが、その当時「アカシア」と呼ばれたために、後々大変混乱することになります。
やがて、「本当のアカシアではない」という意味で「ニセアカシア」とも呼ばれるようになりました。
ハリエンジュにとっては、大変迷惑な話です。
本来のアカシアは、熱帯、亜熱帯原産の「ネムノキ科」の植物で、花は黄色がほとんどです。
代表的なのが、あの「ミモザ」と呼ばれているミモザアカシアなどです。
日本の歌謡曲などで、「アカシア」を歌った曲のほとんどは、ニセアカシアのことだそうです。(「アカシアの雨が止むとき・・・♪」「アカシアの花の下で・・・♪」等々。)
ニセアカシアについてのお話は、下記の「内藤景代のフォト・エッセイ」をご覧下さい。
こちらは、正真正銘のミモザ・アカシアです。(下の写真)

いち早く、春を告げた黄色い花はすでになく、今は沢山の実をつけています。
それを目当てにやってきたのが、野生化したインコたち、ワカケホンセイインコの集団です。
よく観察すると、片脚を使って、うまく実をもぎって、しっかりつかんでいます。
(「見たな!」という感じで、コワイですが。)(下の写真)

サヤをしごいて、中の実だけをうまく食べているようです。(下の写真)
食べ終わると、カラをそのまま下へ落としますから、木の下にいる通行人は、パラパラ落ちるカラに、ビックリします。
上を見上げて、大きなインコにまたビックリです。
このサヤの中に入っている実際の実は、とても小さなもので、インコの胃袋を満たすのは大変なようです。
手間もかかりますし・・・。
これに懲(こ)りたのか、非常用にとってあるのか、2,3日は来ましたが、その後はまったく見かけません。

(下の写真)は、7月25日にご紹介のツバメのヒナ。
ある日、巣の下を通ると、こんなことになっていました。
ヒナたちが大きくなって、あまり身を乗り出すので、巣が半分壊れてしまったのです。
ヒナも一旦落ちてしまったのでしょう。
そこで、巣のある家の方が、壊れた巣の代わりに、ダンボールの箱を用意してくれました。
ヒナたちも、いくぶん心細げな様子です。
この位置は、巣の真下ですが、地上から1メートルくらい。
ネコなどのことを考えるとキケンが一杯の高さです。
心配しましたが、一日くらいで、ダンボールはなくなりましたので、2羽は無事に巣立ったのでしょう。
残りの1羽も、無事にいち早く巣立ったと考えたいものです。

![]() 参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
参照 内藤景代の「フォト・エッセイ」
エンジュの実
ニセアカシア
ミモザアカシア ミモザアカシア(2)
● ヨガ・瞑想・自然「内藤景代のフォト・エッセイ」2009年8月号更新しました。
 |
 |
●NAYヨガスクール「猫の集会」生徒さんの写真・エッセイ・演奏 2009年8月号更新しました。
←翌月へ ↑ TOPへ →前月へ
内藤景代の『冥想(瞑想)―こころを旅する本』の一節に、『僕の街には、何も起こらない』という絵本の紹介があります。主人公の少年が道ばたに座り込んで、僕の街は、タイクツで、ツマラナイから、どこか遠い、別世界を夢見て、空想の世界に遊んでいる間に、彼が見ようとしない「現実」、つまり彼が住む街は、次々に事件や、出来事が起こっていく・・という絵本です。 私たちを取り巻く「世界」も、日々刻々と変化しています。 また、最近は仕事が忙しくて、空も、月も見ていない、という方々もおられます。 今、フツーの、ありふれた、まわりの自然は、どうなっているのか? その中で植物や、動物たちは、どのようにがんばって生きているのか? 都会の真ん中に住みながら、スローなまなざしと、自然をいつくしむハートでとらえた姿を、写真でありのままにお伝えできたらと願い、このページを作りました。 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ」の「幕間(まくあい)」としての役目も果たせたら、と思っています。 掲載された写真に関連した内藤景代の「日誌風エッセイ」の過去のページにもリンクしています。循環する「大きなとき」を感じる参考になさってください。 2005/10/15 NAYヨガスク−ル・スタッフ拝 |
|---|
*「月齢」とは 「新月の日から数えた日数のこと」 約29.53で一周する。 *温度、天候などの基準は東京です。撮影地も、主として東京都内です。 *日の出、日の入り、月の出、月の入りは、満月、新月、上弦、下弦の日に表示しています。変化を比べて下さい。 *「二十四節気」とは 簡単にいうと、太陰暦(月の運行が基準)を使っていた時代に、太陽の運行を基準にして、1年を24等分して、季節の変化を正確に知らせるために考案されたもの。1節気は、約15日 →「内藤景代の日誌風フォト&エッセイ」参照 |
|
内藤景代著「BIG ME」(NAYヨガスク−ル刊) 内藤景代著『家庭でできるビューティ「ヨガ」レッスン』(PHP研究所刊) |
| ヨガと瞑想に関するHPのご紹介 |
新しいサイトができました! 1 |
| エヌ エ−ワイ 東京・新宿・ヨガ教室 since1976 | ヨガと冥想(瞑想)NAYヨガスク−ル |
| NAY SPIRIT IS BODY TRIP& MIND TRIP to SOUL in HEART ●内藤 景代(Naito Akiyo)主宰 mail: e@nay.jp http://www.nay.jp/ |
|
| 〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-19 金光コーポ 201 |
専用FAX 03-5934-6723 24時間受付 TEL 03-3203-3831 |