ヨガ(ヨーガ)の基本、方法などを内藤景代の本で学びませんか? ヨガ・瞑想・教室(東京・新宿) NAYヨガスクール
|
nature photo 撮りたて癒しの写真! 2007/10/31(水)
|
| ←nature photo&フォトエッセイ(内藤景代)トップへ ←ヨガの基本・方法・効果(内藤景代) TOPへ |
| ● |
● 『からだにいいこと』(詳伝社)07年11月号 【「お昼寝ヨガ」で、脳もカラダも若返る】 掲載中
● 『ベッドの上で簡単にできる「寝ヨガ」レッスン〈快眠・ヨガCD付>』(実業之日本社)重版!販売中。こちらへ→●Amazon
2007/10/31(水) 曇時々晴 月齢19.9 気温(H)20.6度;(L)14.5度 《次の「下弦 」は11/2 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 11/8 (冬の気配が現われてくる頃。
)》
●ヨガ・瞑想・LOHAS風「内藤景代の日誌風フォト&エッセイ」11月1日 更新しました!
●NAYヨガスクール「猫の集会」生徒さんの写真・エッセイ・演奏 2007年11月号更新しました。
2007年11月1日(木) 紅白のミズヒキ(水引 みずひき)花 薄いピンクのシュウメイギク(秋明菊 しゅうめいぎく) 季節性ウツ病 立冬 小雪 ツマグロヒョウモン(妻黒豹紋)
蝶オス 目玉模様 豹の目 トウワタ(唐綿 とうわた)の花 つぼみ ハゲイトウ(葉鶏頭 はげいとう) デュランタ フジ(藤 ふじ)に似た紫の小花 別名タイワンレンギョウ(台湾連翹) (わたしは、石垣の一部です)と、眠る猫
秋の夕方の空と雲(下の写真)

2007/10/30(火) 晴後曇 月齢18.9 気温(H)21.9度;(L)16.4度 《次の「下弦 」は11/2 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 11/8 (冬の気配が現われてくる頃。
)》
2007/10/29(月) 曇時々晴 月齢17.9 気温(H)25.6度;(L)16.0度 《次の「下弦 」は11/2 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 11/8 (冬の気配が現われてくる頃。
)》
2007/10/28(日) 快晴 月齢16.9 気温(H)23.7度;(L)12.8度 《次の「下弦 」は11/2 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 11/8 (冬の気配が現われてくる頃。
)》
●内藤景代のヨガ、瞑想、呼吸法の短期講習・セミナー「集中レッスン」が行われました。
次回の「集中レッスン」は11月25日(日)pm1:00-5:00です。
詳しくはこちらへ。
台風一過の秋晴れで、この日は一日中都内のあちこちから、富士山がよく見えました。
公園の一角に咲いていたノハラアザミ(野原薊)にスジグロシロチョウが、とまる、というより「張り付いて」いました。
秋も深まってくると、チョウの動きも緩慢になって、人を恐れなくなってきます。
人どころではないのでしょう。
刻々と迫り来る終わりの時期・・・。
このまま、ずっとアザミに張り付いていたい、そんな思いを感じます。
意外かも知れませんが、スジグロシロチョウは、日本在来の種で、モンシロチョウの方が帰化種です。

下記の10/23とは別な公園の池は、もう冬の常連さんが出そろったようです。
オナガガモ以外では、キンクロハジロ、ホシハジロ、ハシビロガモ・・。
写真の奥と手前、黒い顔、金色の眼、チョンマゲで、独特の雰囲気をかもしているのがキンクロハジロです。
「白い妖精」と呼ばれる鳥もいれば、このキンクロのように、失礼にも「黒い魔人(?)」などと呼ばれる鳥もいます。
ホシハジロ(右の茶色の頭)などは、人のエサは食べないといわれていますが、キンクロは、オナガガモなどと競って食べます。
コワイ、性格悪そうなどいう声を聞きますが、確かにあまり物怖じしない性格のようです。
しかし、あのチョンマゲのような冠羽のファンは大勢います!
(長いチョンマゲで白黒はっきりしているのがオスです。)
(下の写真)は、キンクロハジロの飛翔。


![]() 参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
アザミ 2003/6/4 2002/11/5
渡り鳥 2003/10/23 2003/4/15 2003/1/29
2007/10/27(土) 大雨 月齢15.9 気温(H)19.1度;(L)14.1度 《次の「下弦 」は11/2 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 11/8 (冬の気配が現われてくる頃。
)》
台風20号が関東南部に接近。一日中大雨。
2007/10/26(金) 雨後一時曇 月齢14.9 気温(H)19.0度;(L)14.9度 《次の「下弦 」は11/2 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 11/8 (冬の気配が現われてくる頃。
)》
日の出 5:56 日の入り 16:53 月の出16:37 月の入り5:40 (10/26満月)
日の出 5:50 日の入り 17:02 月の出12:54 月の入り22:40 (10/19上弦)
2007/10/25(木) 晴後曇 月齢13.9 気温(H)21.5度;(L)13.6度 《次の「 ●満月 」は10/26 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 11/8 (冬の気配が現われてくる頃。 )》
2007/10/24(水) 二十四節気は「霜降(そうこう) ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。) 晴 月齢12.9 気温(H)20.5度;(L)13.3度 《次の「 ●満月 」は10/26 次 の二十四節気は「立冬(りっとう) 11/8 (冬の気配が現われてくる頃。 )》
2007/10/23(火) 曇時々晴 月齢11.9 気温(H)23.4度;(L)15.6度 《次の「●満月」は10/26 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
だいぶ寒くなってきましたので、ひょっとしてと思い、公園の池に寄ってみると、やはりオナガガモが渡ってきていました。
いままで静かだった池が、急ににぎやかになりました。
ここの住人であるカルガモたちは、これをどう思っているのでしょう。
人間世界だと、大変なことになりそうですが・・。
別な池には、キンクロハジロ(例の白黒模様のパンダ風のカモ)もやってきたそうです。
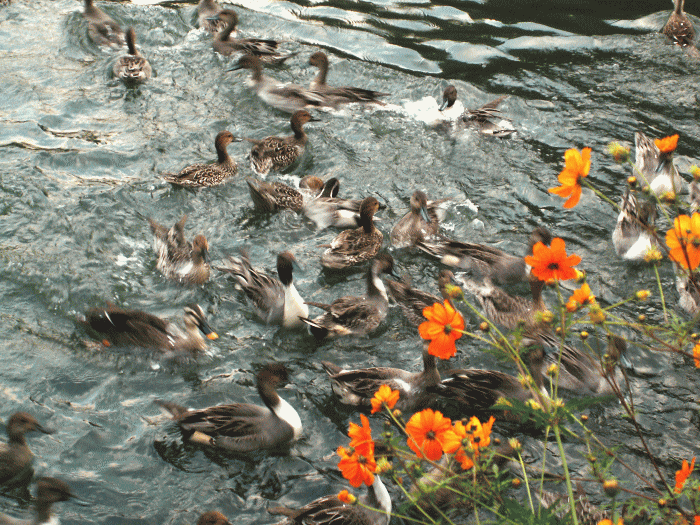
ヤブカラシの葉の上にとまっているチョウは、キタテハでした。
キタテハも下の10/6のルリタテハのように、秋に生まれたものは、成虫のまま、つまりこのままの姿で、越冬するそうです。
それにしても、この羽根の縁の、ちぎったようなギザギザは、すごいですね。
秋型(越冬する秋生まれ)は夏型より外縁部の”ギザギザ”がより強くなる、ということです。
ギザギザが多い方が、春まで生き残る確率が高かった結果でしょう。
冬は暗い林の中などにいる時間が長く、落ち葉などのうえにとまっているときなど、ギザギザが多い方が目につきにくいからでしょうか?

(下の写真)は10月19の上弦の翌日、夕焼けと月の様子です。

![]() 参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
オナガガモ 2003/10/28 2004/12/6
2007/10/22(月) 晴 月齢10.9 気温(H)21.8度;(L)13.4度 《次の「●満月」は10/26 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/21(日) 晴 月齢9.9 気温(H)21.8度;(L)13.7度 《次の「●満月」は10/26 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
![]() 2007/10/20(土) 薄曇時々晴 月齢8.9 気温(H)21.2度;(L)13.6度 《次の「●満月」は10/26 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/20(土) 薄曇時々晴 月齢8.9 気温(H)21.2度;(L)13.6度 《次の「●満月」は10/26 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/19(金) 曇後一時雨 上弦 月齢7.9 気温(H)21.1度;(L)13.9度 《次の「●満月」は10/26 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
日の出 5:50 日の入り 17:02 月の出12:54 月の入り22:40 (10/19上弦)
日の出 5:43 日の入り 17:12 月の出5:34 月の入り16:55 (10/11新月)
川沿いの桜の木の上で、コサギが羽繕(はづくろ)いをしていました。
いつも人は、下の川底で、魚をとっているコサギを見下ろして眺めていますから、立場が逆転です。
コサギの方が、上から人間を睥睨(へいげい)して、ゆったりと構えています。
長いクチバシで、器用に羽根を梳く(す)くようにしています。
下の方の写真は、コサギのネジリのポーズ(?)です。



こちらは、セセリチョウとブルーサルビアの花。
黒い大きな眼がカワイイですね。
ブルーサルビアの花弁を踏み台にして、その上の花に長い口吻(ストロー状の口)を入れて、蜜を吸おうとしているところです。
「セセリ」というのは、一説には花の蜜を「せせる」という動作からつけられたと言われています。
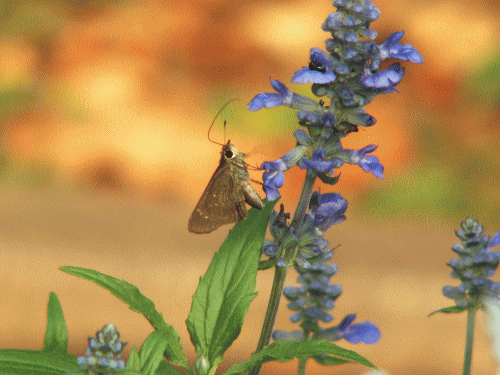
![]() 参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
コサギ 2003/12/29 2004/3/24 2006/5/16
セセリチョウ 2003/8/9
2007/10/18(木) 晴時々曇 月齢6.9 気温(H)21.0度;(L)14.9度 《次の「上弦」は10/19 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 (
露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/17(水) 晴後曇 月齢5.9 気温(H)21.7度;(L)14.8度 《次の「上弦」は10/19 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 (
露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/16(火) 曇後時々雨 月齢4.9 気温(H)17.9度;(L)14.9度 《次の「上弦」は10/19 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 (
露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/15(月) 曇 月齢3.9 気温(H)22.0度;(L)16.7度 《次の「上弦」は10/19 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 (
露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
秋になって、スズメガ(雀蛾)の緑色のオオスカシバが少なくなると、同じスズメガのホシホウジャク(星蜂雀)が見られるようになります。
オオスカシバのように、ホバリング(空中で羽ばたきしながら静止)をしながら、花の蜜を吸いますが、体色がオオスカシバの緑色に対して、ホシホウジャクは、ハチに似た茶と黒が混ざった色で、翅(はね)は、スカシバのように透明ではありません。
移動が早く、写真を撮るのに苦労します。
どちらも、昼間活動する蛾です。
ホシホウジャクとホウジャクは、とても似ていますが、下記の「内藤景代の日誌風フォト&エッセイ」でその違いを確認してみてください。
(上の写真)は、アベリアから吸蜜するホシホウジャクを真横から撮ったもの。
(中の写真)は真上から。
首の後の赤い色は、どうもキズのようです。
(下の写真)は吸蜜前後に、長い口吻(こうふん)を丸めているところです。



![]() 参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
ホウジャク 2002/10/24 2002/10/25 2002/11/5
スカシバ 2003/9/20
2007/10/14(日) 曇 月齢2.9 気温(H)19.9度;(L)16.1度 《次の「上弦」は10/19 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 (
露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/13(土) 曇一時晴 月齢1.9 気温(H)21.8度;(L)18.2度 《次の「上弦」は10/19 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 (
露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/12(金) 晴時々曇 月齢0.9 気温(H)26.2度;(L)19.9度 《次の「上弦」は10/19 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 (
露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/11(水) 曇後晴 ●新月 月齢29.6 気温(H)24.2度;(L)17.6度 《次の「上弦」は10/19 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
日の出 5:43 日の入り 17:12 月の出5:34 月の入り16:55 (10/11新月)
日の出 5:37 日の入り 17:23 月の出22:22 月の入り12:50 (10/3下弦)
(上の写真) 白い水鳥と静かな池の風景
こころを静める瞑想用のイメージにどうぞ。
(中の写真) 夕方のカワセミ 正面から
(下の写真) オオイヌタデとカルガモ
オオイヌタデ(大犬蓼) イヌタデ(赤まんま)の仲間で、白または淡紅色の花をつけ、2メートル近く高くなるものもあります。
イヌタデは食用になりますが、オオイヌタデは食べられないそうです。



![]() 参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
イヌタデ 2003/9/17
2007/10/10(水) 曇後一時晴 月齢28.6 気温(H)22.3度;(L)17.9度 《次の「●新月」は10/11 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/9(火) 「寒露(かんろ」 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
雨後曇 月齢28.6 気温(H)24.6度;(L)17.6度 《次の「●新月」は10/11 次 の二十四節気は「霜降(そうこう) 10/24 ( 露が冷気によって霜となって降り始める頃。)》
2007/10/8(月) 雨時々曇 月齢27.6 気温(H)18.5度;(L)15.7度 《次の「●新月」は10/11 次 の二十四節気は「寒露(かんろ」 10/9 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
2007/10/7(日) 晴 月齢26.6 気温(H)23.4度;(L)15.7度 《次の「●新月」は10/11 次 の二十四節気は「寒露(かんろ」 10/9 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
2007/10/7(日) 晴 月齢25.6 気温(H)23.4度;(L)15.7度 《次の「●新月」は10/11 次 の二十四節気は「寒露(かんろ」 10/9 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
2007/10/6(土) 晴時々曇 月齢24.6 気温(H)23.5度;(L)17.7度 《次の「●新月」は10/11 次 の二十四節気は「寒露(かんろ」 10/9 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
神奈川県西部震源の地震が続いている。AM3:56 国分寺 震度3。
公園の池の縁で、ルリタテハに出会いました。
雑木林の周辺などで多く生息し、成虫のまま冬を越します。
つまり、ルリタテハは年に3回発生し、その3代目が9月下旬から10月にかけて羽化し、それが成虫のまま越冬するのだそうです。
チョウの「バトン・リレー」のようですね。
このチョウは、越冬する3代目でしょうか?
従って、春は他のチョウより早く、4月ごろには、もう姿を見せ始めます。
2006年3/11 の「nature photo」には、早くも観察されています。
http://www.yoga.sakura.ne.jp/nature-photo-2006-3.html
たいてい翅(はね)を閉じていますが、時々(中の写真・左)のように翅を開くことがあります。
陽に当てて体温を上昇させるためとか、縄張りを主張する目的があるようです。
この写真を見ると、触角をピンとたて、威厳に満ちて、縄張りを主張しているように思えてしまいますが・・。
翅を完全に閉じて、木の幹にとまっていると、樹皮とまったく区別がつきません。(中の写真・右)
(下の写真)は、ルリタテハの横で咲いていた、白いヒガンバナ。




![]() 参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
ヒガンバナ 2002/9/27 2006/10/1 2002/9/19
2007/10/5(金) 晴時々曇 月齢23.6 気温(H)26.5度;(L)19.7度 《次の「●新月」は10/11 次 の二十四節気は「寒露(かんろ」 10/9 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
2007/10/4(木) 晴時々曇 月齢22.6 気温(H)25.6度;(L)19.1度 《次の「●新月」は10/11 次 の二十四節気は「寒露(かんろ」 10/9 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
2007/10/3(水) 曇 下弦 月齢21.6 気温(H)22.6度;(L)19.6度 《次の「●新月」は10/11 次 の二十四節気は「寒露(かんろ」 10/9 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
日の出 5:37 日の入り 17:23 月の出22:22 月の入り12:50 (10/3下弦)
日の出 5:32 日の入り 17:32 月の出17:36 月の入り5:39 (9/27満月)

なかなかスッキリしない、お天気が続きますが、モミジのなかには、こんなに美しく紅葉しているのもあります。
また、この時期には、ひっそりと清楚に咲くジュウガツザクラ(十月桜)もみられます。
ジュウガツザクラは、コヒガンザクラの園芸品種で、秋と春の2回咲きます。
よく神社の境内などに植えられていますので、探してみてください。
春の桜が満開の時期を思い出します。


![]() 参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
参照 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ
紅葉 2006/12/2 2003/11/8 2005/12/2
ジュウガツザクラ 2003/2/8 2002/10/25
2007/10/2(火) 雨後曇 月齢20.6 気温(H)22.7度;(L)17.2度 《次の「下弦」は10/3 次 の二十四節気は「寒露(かんろ」 10/9 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
2007/10/1(月) 曇時々雨 月齢19.6 気温(H)19.9度;(L)16.4度 《次の「下弦」は10/3 次 の二十四節気は「寒露(かんろ」 10/9 (露が冷気にあって凍りそうになる頃。冬鳥が渡ってきて、菊が咲き始める。)》
午前2時21分ごろ、神奈川県西部震源の地震。箱根町で震度5強。
●NAYヨガスクール「猫の集会」生徒さんの写真・エッセイ・演奏 2007年10月号更新しました。
●ヨガ・瞑想・LOHAS風「内藤景代の日誌風フォト&エッセイ」10月1日 更新しました!
2007年10月1日(月)白い花。ナス科。ヒヨドリジョウゴ(鵯上戸 ひよどりじょうご)の緑の果実と白い花。翡翠(ひすい)の玉(ぎょく)のような小さな緑の実は、秋に赤い実になる。フユサンゴ(冬珊瑚
ふゆさんご :玉珊瑚 タマサンゴ、クリスマス・チェリー、ビッグボーイ)は、プチ・トマトの大きさの赤い実が今みのる。丸い「観賞トウガラシ」にそっくりで「偽トウガラシ」が学名で、「食用不可!」。どちらも有毒。エンジュ(槐 えんじゅ:槐樹 かいじゅ;黄藤 きふじ)の果実は、豆がいっぱい。1年に一度、ひと夜かぎり咲く、月下美人(げっかびじん ゲッカビジン)の大輪の白い花を見た、秋分の翌日の夜
内藤景代の『冥想(瞑想)―こころを旅する本』の一節に、『僕の街には、何も起こらない』という絵本の紹介があります。主人公の少年が道ばたに座り込んで、僕の街は、タイクツで、ツマラナイから、どこか遠い、別世界を夢見て、空想の世界に遊んでいる間に、彼が見ようとしない「現実」、つまり彼が住む街は、次々に事件や、出来事が起こっていく・・という絵本です。 私たちを取り巻く「世界」も、日々刻々と変化しています。 また、最近は仕事が忙しくて、空も、月も見ていない、という方々もおられます。 今、フツーの、ありふれた、まわりの自然は、どうなっているのか? その中で植物や、動物たちは、どのようにがんばって生きているのか? 都会の真ん中に住みながら、スローなまなざしと、自然をいつくしむハートでとらえた姿を、写真でありのままにお伝えできたらと願い、このページを作りました。 内藤景代の「日誌風フォト・エッセイ」の「幕間(まくあい)」としての役目も果たせたら、と思っています。 掲載された写真に関連した内藤景代の「日誌風エッセイ」の過去のページにもリンクしています。循環する「大きなとき」を感じる参考になさってください。 2005/10/15 NAYヨガスク−ル・スタッフ拝 |
|---|
*「月齢」とは 「新月の日から数えた日数のこと」 約29.53で一周する。 *温度、天候などの基準は東京です。撮影地も、主として東京都内です。 *日の出、日の入り、月の出、月の入りは、満月、新月、上弦、下弦の日に表示しています。変化を比べて下さい。 *「二十四節気」とは 簡単にいうと、太陰暦(月の運行が基準)を使っていた時代に、太陽の運行を基準にして、1年を24等分して、季節の変化を正確に知らせるために考案されたもの。1節気は、約15日 →「内藤景代の日誌風フォト&エッセイ」参照 |
|
内藤景代著「BIG ME」(NAYヨガスク−ル刊) 内藤景代著『家庭でできるビューティ「ヨガ」レッスン』(PHP研究所刊) |
| ヨガと瞑想に関するHPのご紹介 |
新しいサイトができました! 1 |
| エヌ エ−ワイ 東京・新宿・ヨガ教室 since1976 | ヨガと冥想(瞑想)NAYヨガスク−ル |
| NAY SPIRIT IS BODY TRIP& MIND TRIP to SOUL in HEART ●内藤 景代(Naito Akiyo)主宰 mail: e@nay.jp http://www.nay.jp/ |
|
| 〒160-0022東京都新宿区新宿6-27-19 金光コーポ 201 |
専用FAX 03-5934-6723 24時間受付 TEL 03-3203-3831 |